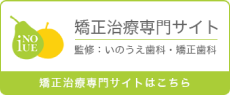こんにちは、歯科衛生士の野田です。
8月7日は立秋でした。暦の上では秋らしいですが、あっつい(;’∀’)ですね~~。皆様今年の夏はいかがお過ごしですか?
『コロナさん』も、姿隠したまま私たちの生活の中にニューっと侵入してきて、ドーンと居座ったままなかなか出ていかないから、ますます困った幽霊👻みたいな厄介な存在になっていますよね。
この招かざる客は、どうしたら出ていってくれるんでしょうか😡
いのうえ歯科・矯正歯科には、院長や副院長チョイスの書籍を借りて読むことが出来る《院内図書館》があります。
そこで見つけた本、【医師が実践する 病気にならない自然な暮らし】 。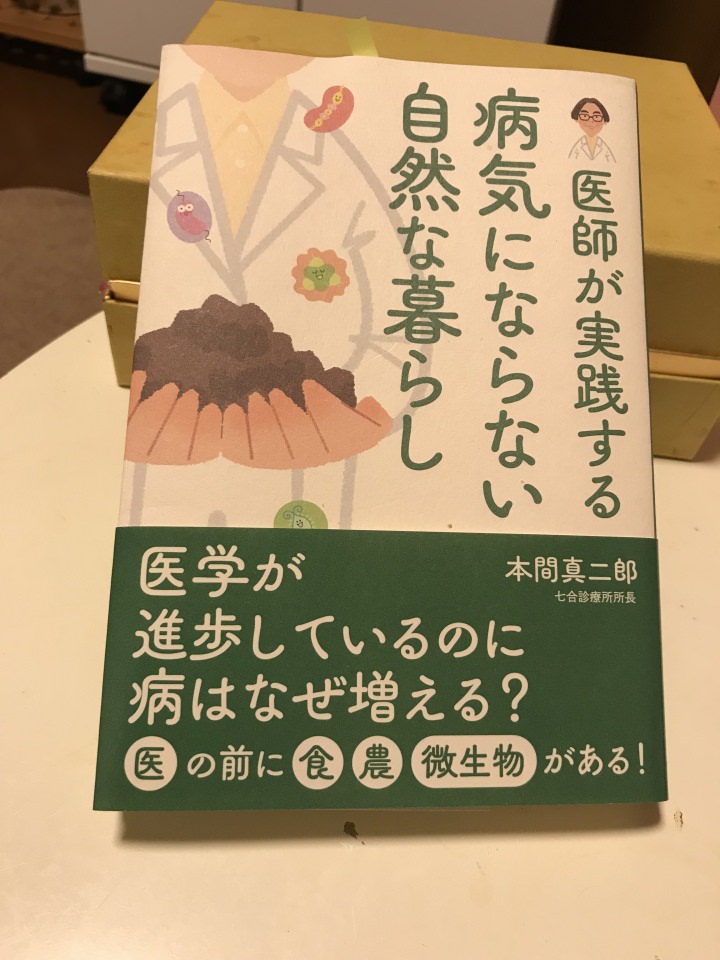
初老期に突入している私には魅力的なタイトルでしたので、見つけた瞬間すぐに手に取ってしまいました😅。
著者である本間先生は、もともと最先端の西洋医学に取り組まれていた先生ですが、
ある日、
現代の医学は、発熱やがんやアレルギーなど『結果』として出た病気に対しての対症療法にすぎない。
どうしてこうなったのかという病気の『原因』には全く対応していない。
だから、一時的に回復しても『原因』を変えないことには同じことの繰り返しである!
対症療法より根本療法が治療の本質である!
本の帯にも記してあるように、
医の前に食・農・微生物がある!と考えられました。
私たちの身体は食べた物を原料としてできているのだから、『食』が大きく関係している。
そしてその食を生み出しているのが『農』であり、農で食べる物を作っているのが『土』であり、土の中の『微生物』であると。
そこで本間先生は、
最先端の医療から離れ、田舎で診療所を開きながら、いわゆる昔ながらの土づくり農法を実践探求され、食べる物も加工食品は使わず、味噌や醤油、酢などの調味料まで天然の麹菌を使う方法で手作りされ、昔ながらの自然な生活を営まれています。
私たち人間は、目には見えないけど体の中や周辺は常在菌という微生物で覆われていて、昔から人はその微生物と共存しているがこそ丈夫な体を保っていたそうです。
悪者としか思っていなかった寄生虫でさえも、人の体の中で免疫系のコントロールする仕組みを持っていることが近年わかったそうです。
農業技術の進歩、農薬や除草剤の開発、化学物質や薬の開発、そして過剰な抗菌・除菌グッズ、洗剤やシャンプーなどなんの疑いもなく毎日使ってる日用品であっても化学物質が使われているので、
それらが微生物を排除し、微生物が減少することによって、それが回りまわって私たちの体の中の腸内細菌叢にまで影響し、腸内細菌が関わっている免疫細胞やホルモンの働きを阻害し、自己免疫力が低下して様々な病気を引き起こしている可能性があると書かれていました。
確かに、コロナさんが流行ってからは特に、過剰なほどに殺菌を意識していますよねー。見えない菌は悪いもの!!みたいな意識は強いですよねー。
こんなに気を付けているのに、『コロナさん』は一向に終息しない!!どころかますます脅威をさらして、一体いつまで続くの~~(>_<)って困った状況ですよね。
メディアでも、《ういずコロナ》とか《共存》とか言っていますけど、私たちの免疫力を上げないことには現状打破は出来ないことではないかと、この本を読んで感じました。
こんなにいろんな食品が身近にある日常で、それに慣れてしまっている私たちが、急に本間先生のように自然な暮らしを実践することはすぐには出来ないことだと思います。
でも、毎日の食べる物に関して、食品添加物も化学物質ですから、腸内細菌にダメージ与える大きな要因となるらしいので、
ちょっとだけインスタントや加工食品を減らすとか、食品の裏面表示をみて出来るだけ添加物の少ないものを選ぶとかは出来ると思います。
出来ることから始めてみようと思いました。
本間先生もいまだ探求中のようですので、この本に書かれていることがすべて正しいとは言い切れないとは思いますが、私にとっては衝撃の一冊であったし、とても学ぶことの多かった本でした。
良かったら皆さんも読んでみてください。
免疫力を上げるには、《食》も大事ですが、《呼吸》も大事ですよね。
私たちの体は37兆個もの細胞で出来ています。
細胞を健康に維持していくためには栄養も大事ですが、細胞をしっかりと機能させるためには酸素も必要です。
しっかりと細胞に酸素を供給するためにはどんな呼吸が良いのでしょうか。
そして、呼吸は姿勢にもそして歯並びにも大きく関係しています。(歯並びの治療中の方には耳タコですよね。😀)
健康のためにはどんな呼吸が良いのでしょうか。
先日、口呼吸を鼻呼吸にかえていく【あいうべ体操】の考案者である内科医の今井一彰先生の話を拝聴する機会がありました。その時にご紹介いただいた2冊の本をこの度入手いたしました✌。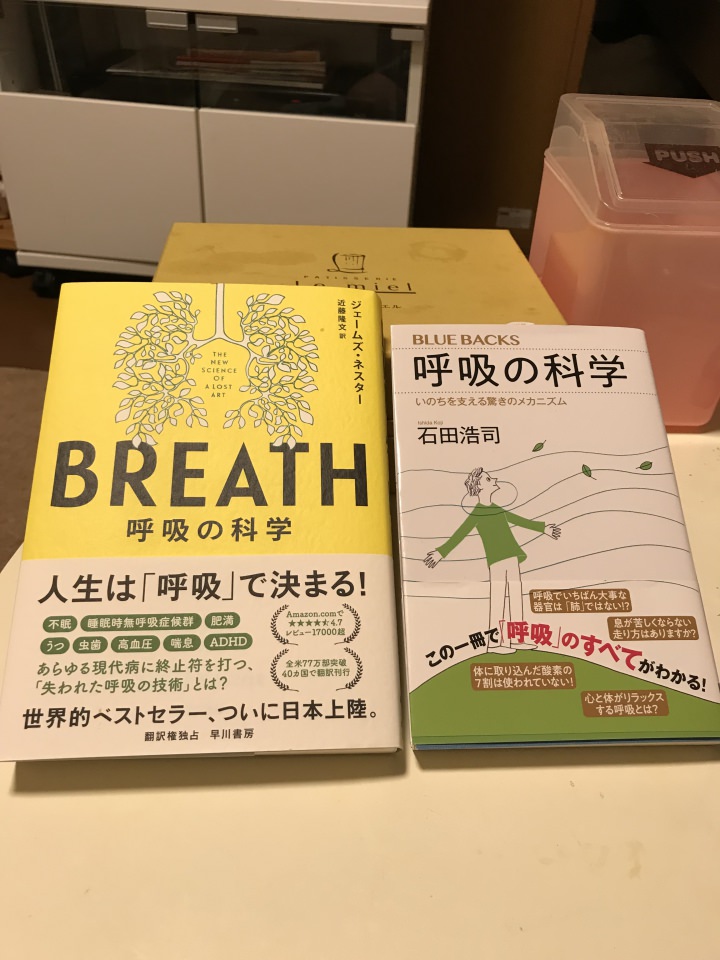
もうすぐお盆休みとなりますが、今年も『コロナさん』の影響で、せっかくのお盆も静かなお盆となりそうです。時間が出来そうですので、今度はこの2冊で学んでみようと思っています。
またご報告いたしますね(´▽`*)。
では、皆さん、二度と訪れないこの夏を大切にお過ごしくださいね。